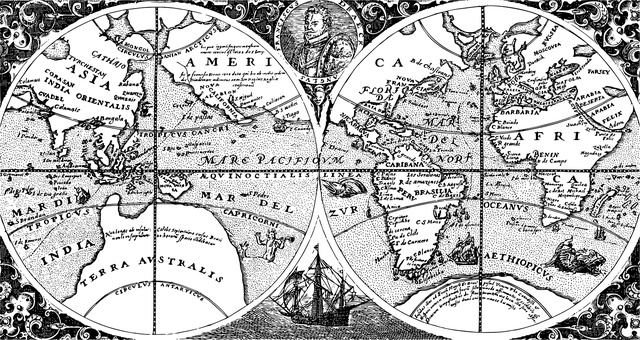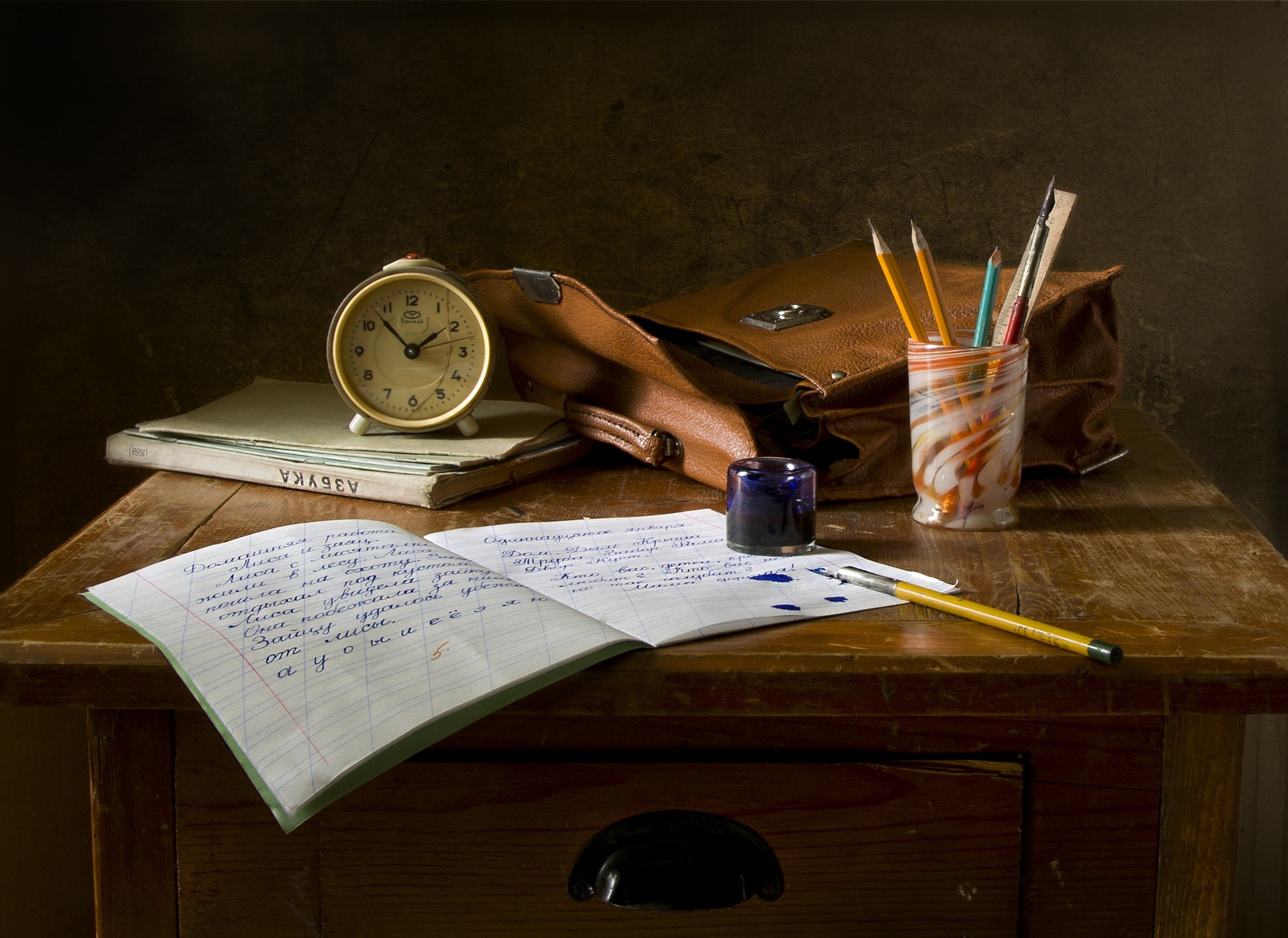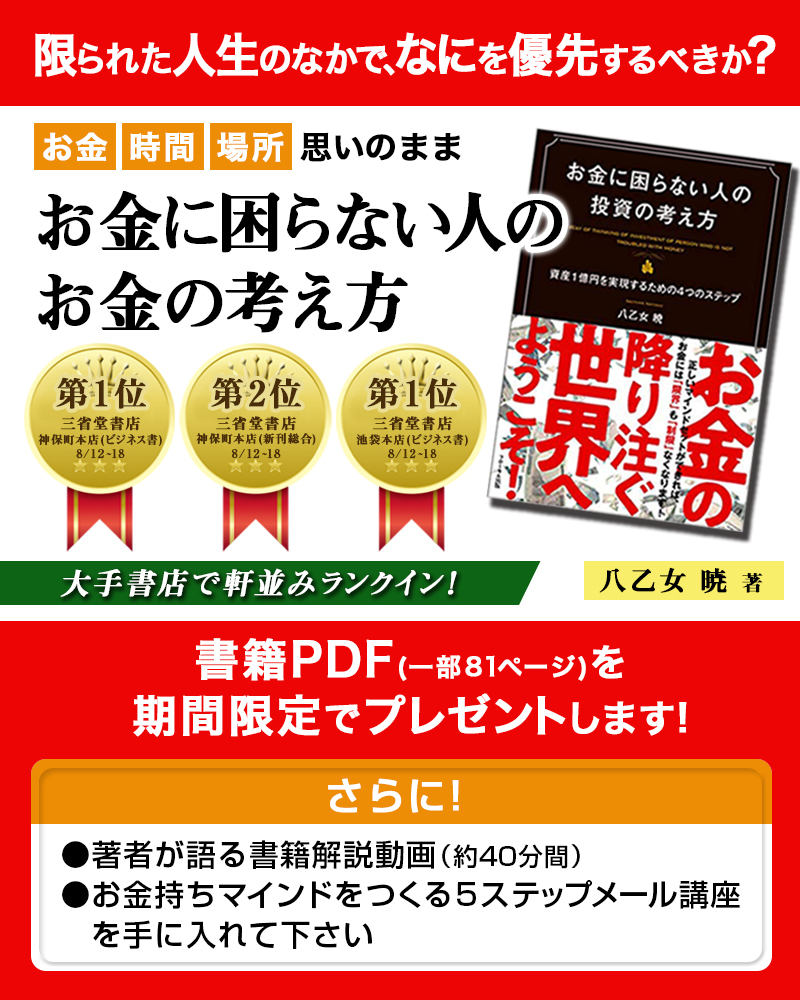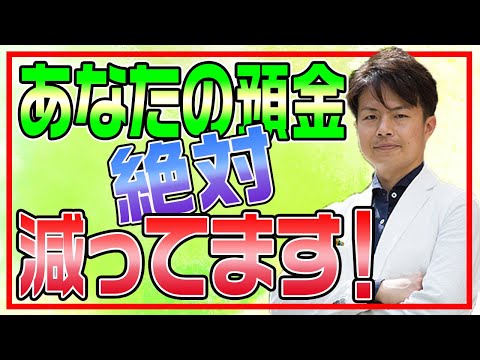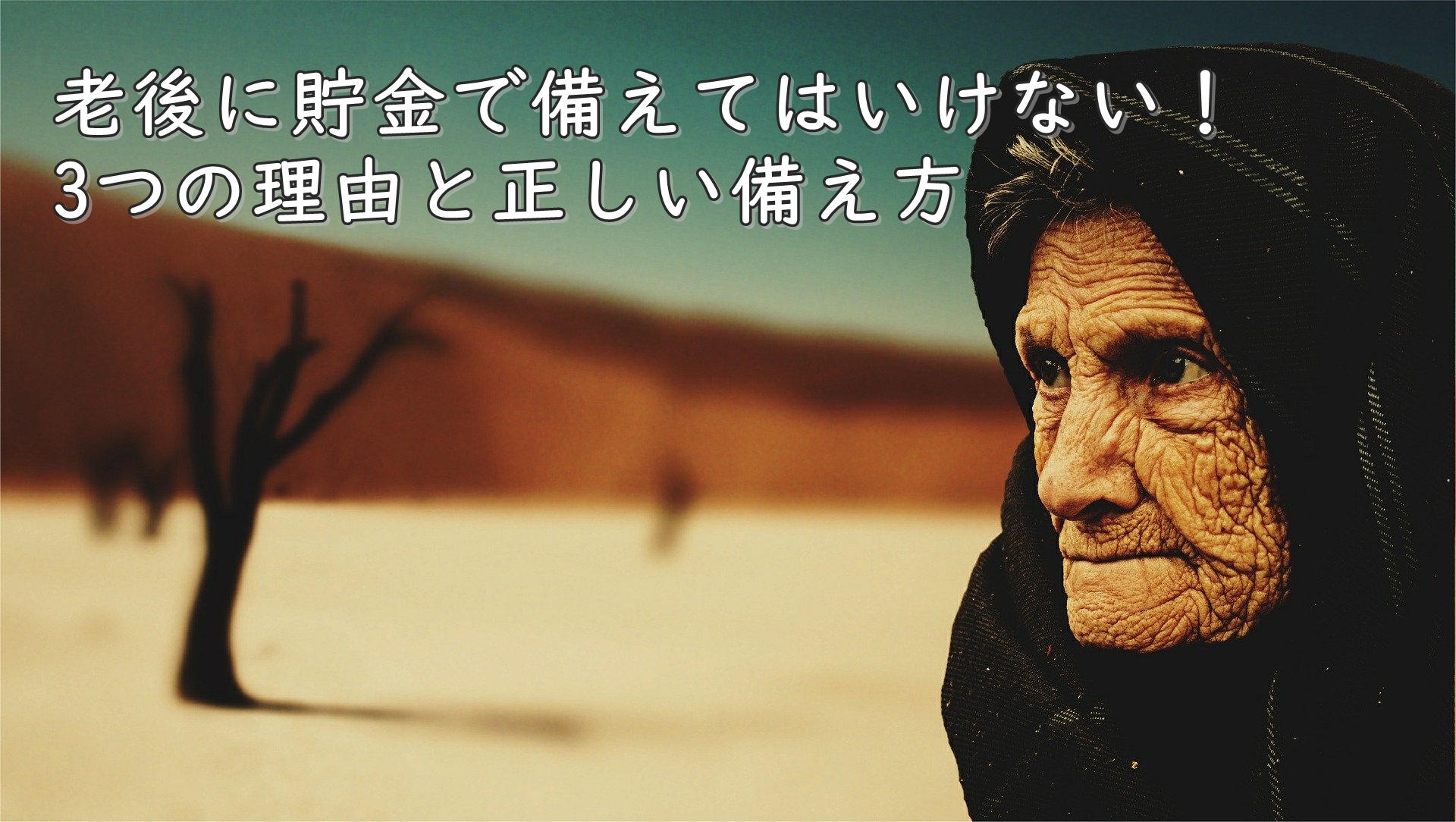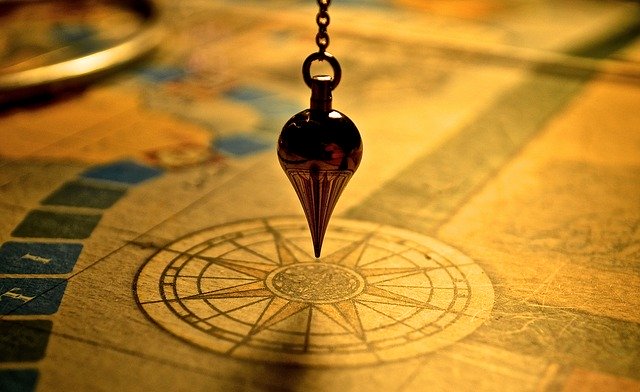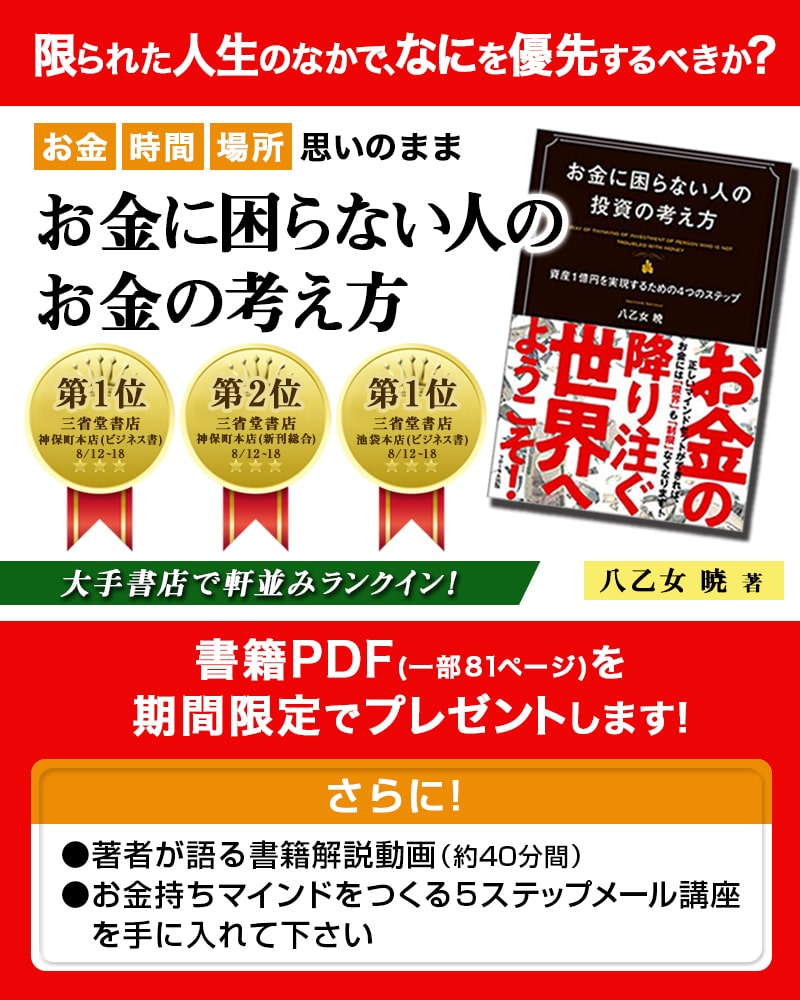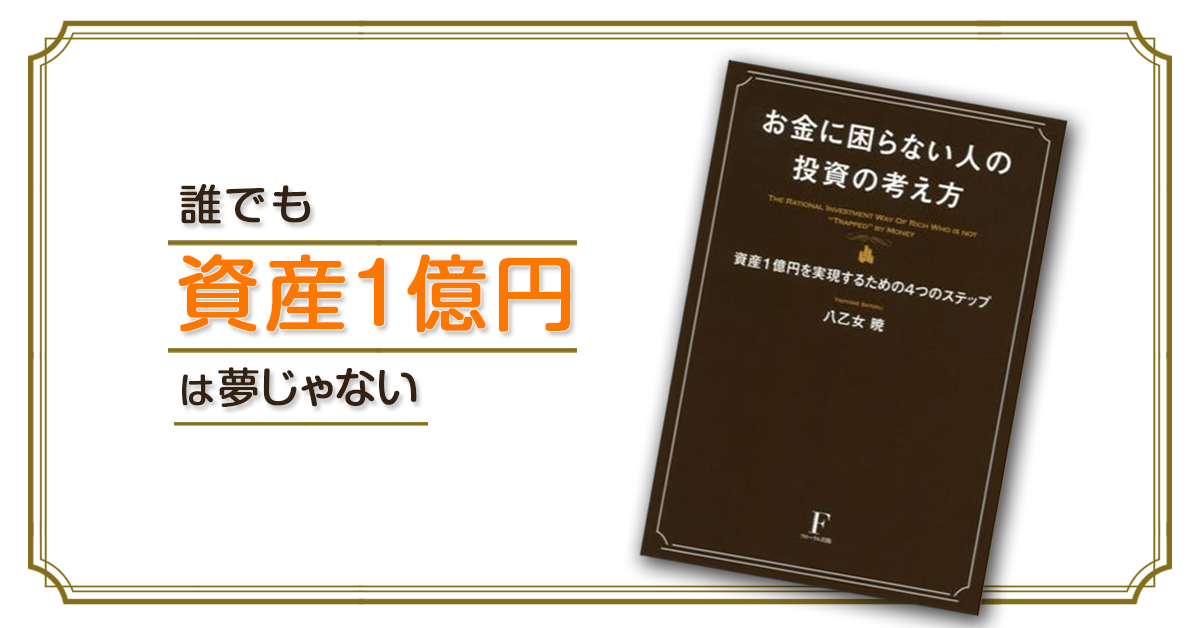2020/04/30 タイトル・目次・本文をリライトしました
1. かえって損する分散投資の真実とワナ
投資では、初心者の方でも、
「タマゴはひとつのかごに盛るな」
「いろいろな資産に分散して投資せよ」
などと分散投資を勧める情報を耳にしたことがあると思います。
しかし、この「分散投資」は正しく意味を理解し、活用していないと、
むしろ、投資で損してしまう人すらいるものです。
本記事では、みなさんが正しく「分散投資」を使いこなせるよう、
その本当の意味と活用法を詳しく解説する完全ガイドとなっています。
2. 分散投資の方法
2-1. 投資対象の分散
不動産や株式、債券など、投資する対象のタイプをいくつか組み合わせるのが、「投資対象の分散」です。
このことによって、株式の利益が出づらい時期に、債券で利益を確保するなど、特定の投資対象のパフォーマンスにすべてを左右されるリスクを避けることができます。
具体的には、好況や不況の際に値動きが相反しているもの、あるいは、価格変動が大きいものと小さいもの、などというように分散をしていきます。
2-2. 投資エリアの分散
投資先を、いくつかの国やいくつかのエリアに分けて投資するのが「投資エリアの分散」です。
例えば、株式に投資する場合には、日本市場だけでなく、アメリカ市場、ヨーロッパ市場、そして、新興国市場などに分けて投資をしておきます。
また、具体的な分散の方法としては、先進国と発展途上国、アジア・北米・EU・その他のエリアなどのように、ある特定の国・エリアの経済や政治にすべての投資が影響されないようにしておきます。
2-3. 投資通貨の分散
日本だけにいると感じずに生活できてしまいますが、そもそも通貨とは、日々実際の価値が変動しているものです。
他の通貨との交換比率である「為替」、例えば「1米ドル=107円」のようなものが刻々と動いているのもそうですし、そもそも発行している国の信用力の変化がその価値を左右しています。
そのため、日本円など一つの通貨で投資することは、その国の行末にすべての投資の結果を委ねてしまうことになります。
具体的な対応としては、生活する国の通貨、資産を守る国の通貨、資産を増やす国の通貨、といった形で、3区分くらいを持つのが良いでしょう。
とかく日本人は、日本円の価値を強く信用していますが、投資家に限らず通貨の分散は世界の常識ですので、注意しましょう。
なお、他にも売り買いのタイミングのリスクを避ける「時間の分散」や投資対象が同じでも投資する「金融機関の分散」など、
分散の種類と具体的方法を詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
3. 分散投資の2つの真実
3-1. 利益と損失を相殺して、リターンのばらつき(=リスク)を小さくすること
では、あらためて「分散投資」の本当の意味を確認しておきましょう。
それは、
『利益と損失を相殺して、リターンのばらつき(=リスク)を小さくすること』
です。
投資商品のパフォーマンスは、良かったり悪かったり、銘柄や時期によって、当然さまざまな変化をします。
このパフォーマンスの「デコボコ」をならすのが、分散投資の1つ目の意味です。
また、経済学ではこの「デコボコ(リターンのばらつき)」を「リスク」と呼びます。
そのため、投資対象の分散などによって、投資の「リスク」を下げることができるわけです。
そして、実はよく注目しておくべきなのは、前半の
『利益と損失を相殺して』
の部分です。
この部分に注目すると、もう一つの分散投資の意味が見えてきます。
3-2. 大きな損失の可能性を避ける代わりに、大きな利益の可能性も捨てること
パフォーマンスの「デコボコ」をならす、ということは、実はメリットばかりではありません。
『大きな損失の可能性を避ける代わりに、大きな利益の可能性も捨てる』
ことに繋がります。
つまり、分散で得られる以上の大きな利益(だけ)を得たい人にとっては、分散などしてはいけないのです。
大きな利益を望む場合は、大きな損失の可能性も裏返しに受け入れる必要があるということです。
①損益の「デコボコ」を相殺することで、全体として利益を安定化させる
②①の安定化と引き換えに、大きな利益を得る可能性も捨てる
4. 分散投資の2つのワナ
4-1. 必ず分散投資すべき、ということはない
先程の分散投資の本当の意味を考えると、「投資では全員が分散をすべき」というような話は、実際は間違いなのです。
分散すべきかどうかは、その人の「リスク許容度(資産状況や好み)」と「投資のゴール(目的)」による、ということになります。
投資のゴールが、金額的に大きく・時間的に近いほど、分散は向かないですし、
金額的に小さく・時間的に遠いほど、分散しても良いということになります。
例えば、何十年もゆっくりと時間をかけて、老後の資産1億円をつくりたい主婦の方なら、
分散してリスクを減らしても良い(その代わりリターンが劇的に高まることもない)ということになります。
一方で、短期間でセミリタイヤを果たしたいサラリーマンの方なら、分散のしすぎはゴールへの到達を遅くしてしまいます。
(また、通常はリターンだけでなく投資の元本を増やすための、投資以外の努力もしなくてはいけません。)
このことをよく理解せずに、「分散投資は投資の常識だ」などと考えて投資をしてしまうと、
かえって自分の目標にまったく到達できないことにもなりかねません。
4-2. ”安全な分散投資”をつづけられないワケ
さらに、分散投資が必要な人でも、実はけっこう分散投資を続けられない点にとても注意が必要です。
例えば、あなたが株式と債券に分散して長期投資をしていたとしましょう。
そんな最中に、世界大恐慌やコロナショックのような世界同時株安が起きました。
あなたの心は揺れます。
せっかく分散投資をしていたけど、株式の部分は換金するか、別の投資対象に入れ替えた方が良いのではないか、そう思うようになります。
すると、いつの間にか、あなたの株式ポートフォリオは消え失せ、現金や他のアセットに入れ替わっていることになります。
結果、あなたが最初に描いた分散投資は崩れてしまうばかりか、ポートフォリオの入れ替えなどで手数料がかさむことになります。
本来、分散投資は「ある投資対象が良いときでも悪いときでも、同じように分散をし続ける」ことに意味があります。
これによって、全体として長期間で見ると、パフォーマンスが安定化されるのです。
しかし、あなたが自分でその配分を決めている場合、中長期に続けることがいろいろな理由で難しくなってしまうのです。
(また、もし自分が未来を感じる投資対象だけに投資をしたくない、という場合には、分散投資をしない方が良い、ということになります。)
このことは、分散投資を実際にやってみるまで、誰も気づかないワナですので、十分に注意が必要です。
①分散投資は誰もがやるべきものではない。自分の目標に合っているか事前に確認しよう。
②分散投資はさまざまな理由で続けられなくなることが多い。大きな盲点なので注意しよう。
5. 分散投資の基礎:現代ポートフォリオ理論(MPT)
5-1. 分散投資を支える、現代ポートフォリオ理論(MPT)
少々難しそうな言葉が出てきましたが、これはハリーマーコウィッツという経済学者が考えた投資についての理論です。
彼は、この現代ポートフォリオ理論(Modern Portfolio Theory)でノーベル賞を受賞しています。
細かい理屈はさておき、この理論の投資家にとって役立つ結論は、
「パフォーマンスが相関していない複数商品に投資することで、
リターンを保ちながらも、リスク(リターンのばらつき)を軽減できる」
ということです。
いまでは、あたり前のように知っている金融界の人ばかりですが、
当時は非常にセンセーショナルな研究として注目を集めました。
例えば、同じ年利10%を目指す場合でも、ただ投資商品を組み合わせるだけで、
リスク(リターンのばらつき)を下げることができるわけです。
将来の結果を絶対にコントロールすることのできない投資において、
自分で管理できるポートフォリオで結果を良くしようとするこの理論はとても衝撃的だったのです。
いまでは、分散投資そのものは言葉としては馴染みのある方も多くなりましたが、
そのベースはこの現代ポートフォリオ理論にあります。
5-2. 分散投資は「魔法の杖」ではない
先ほどお話したとおり、投資する商品ごとのパフォーマンスが相関していなければ、
リターンのばらつき(=リスク)を抑えられるのが現代ポートフォリオ理論でした。
しかし、現実に適用するには、注意しなくてはいけない点があります。
それは、投資後に、個別商品のパフォーマンスの関係がどうなるかは誰にもわからないということです。
それは、私たちはパフォーマンスの相関を判断するために、過去の情報しか使えないからです。
例えば、株式の収益が下がるときに、債券の収益が上がるものだと思っていたら、実際は両方とも価格が下がってしまった、ということが起きることもあります。
近年は、株式と債券のパフォーマンスが相関することも多くなっており、リスクを下げるつもりが下がらなかった…ということも現実に起きています。
ひとつの商品に依存するよりは勿論良いのですが、複数の商品に分散したからと言って、必ず投資対象の分散の効果が得られるわけではないのですね。
この点も分散投資を行うにあたっては、留意しておくべきことのひとつでしょう。
そのため、個人の必要性という観点でも、現実の不確実性という観点でも、
「必ず分散投資しなくてはならない」
という結論にはならないのですね。
②実際にある投資商品とある投資商品のリターンが相関しないかどうかは事前にはわからない。思ったように分散投資のメリットが得られないこともある。
6. まとめ
ここまで、分散投資の本当の意味とそのワナについて、分散投資の理論的背景までさかのぼってお話をしてきました。
やはり、投資においてのリスク(リターンのばらつき)のとり方は、単に分散に分散を重ねてやたらと減らすのではなく、
個人ごとの『許容度』と『必要性』に応じて、柔軟に調節していかなくてはいけませんね。
本記事が投資で自由な人生をつかみたい皆さまの参考になれば、この上ない喜びです。